ごきげんよう。
「ゼロからのAIフロンティア」へようこそ。
当ブログ運営しているケンタロウです。
「音楽を作ってみたいけど、楽器も音楽理論もわからない…」
そんな悩みを抱えていませんか?
でも、安心してください。
今やAIが音楽を生み出す時代。
しかも、テキストで説明するだけで、まるで作曲家のように音楽が完成するなんて、信じられますか?
今回ご紹介するのは、Googleが開発した注目のAIツール「MusicFX(旧MusicLM)」。
音楽の知識がゼロでも、プロのような楽曲が作れる…そんな夢のような体験を、誰でも無料で始められるのです。
この記事では、
- MusicFX(旧MusicLM)とは何か?
- なぜ音楽理論なしで作曲できるのか?
- 実際の使い方や注意点
について、初心者にもわかりやすく解説していきます。
読み終える頃には、「自分にも音楽が作れる!」と感じてもらえるはずです。
MusicFX(旧MusicLM)とは?
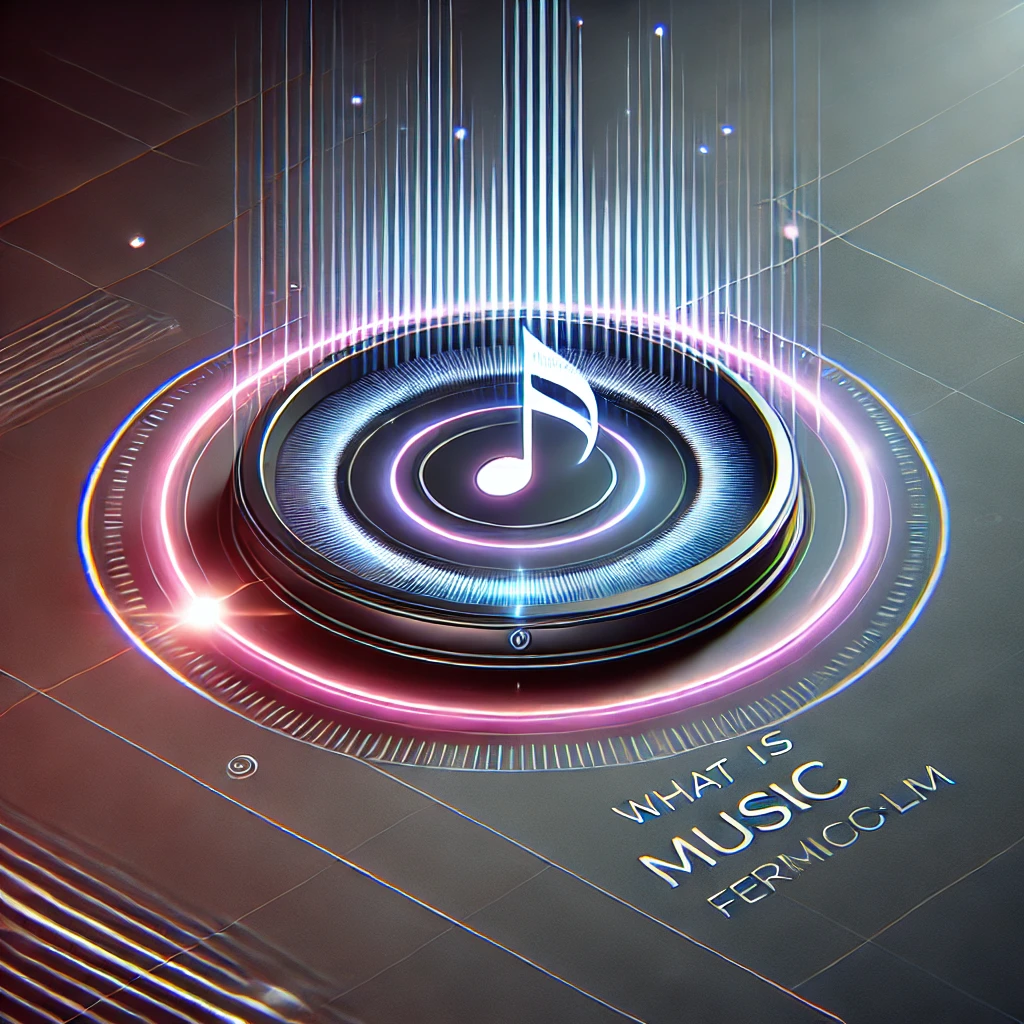
Googleが開発した音楽生成AIツールの概要
音楽制作のハードルを劇的に下げるツールとして注目されているのが、「MusicFX(旧MusicLM)」です。
このAIは、Googleが研究機関DeepMindの技術を基に開発したもので、テキストによる指示だけで音楽を自動生成するという革新的な機能を備えています。
たとえば「リラックスできるピアノ曲」や「激しいドラムとシンセが鳴るエレクトロ」など、イメージを言葉で伝えるだけで、まるでプロが作曲したかのような音源が出力されるのです。
今までの音楽制作には、DAW(音楽制作ソフト)の知識や、打ち込み技術、音楽理論などが求められていました。
しかし、MusicFXはそうした専門スキルが一切不要で、文章で指示するだけという直感的な操作で楽曲を作ることができます。
Googleはこのプロジェクトを通して、誰でも創造力を形にできる世界の実現を目指しており、そのビジョンの中核を担うのがこのMusicFXなのです。
旧名称MusicLMとの違いとは?
「MusicFX」は、以前「MusicLM」という名前で公開されていたプロジェクトのアップグレード版です。
名前が変わっただけではなく、機能面やユーザー体験にも複数の改善が加えられています。
旧MusicLMは、研究論文の一環として限定的に紹介されていた段階で、一般のユーザーが実際に使うことは難しい状況でした。
しかし、MusicFXとして正式リリースされたことにより、より多くの人が実際に体験できる環境が整備されました。
さらに、旧バージョンではユーザーインターフェースが存在せず、専門的な操作や知識が必要だったのに対し、MusicFXではWebベースの直感的なUIが用意され、初心者でも操作しやすくなっているのが特徴です。
また、生成される音質や曲の構成も進化しており、よりリアルで自然な楽曲が完成するようになりました。
このように、単なる名称変更ではなく、「MusicLM」から「MusicFX」へは大幅な進化を遂げたといえるでしょう。
誰に向いている?初心者でも使える理由
MusicFXの最大の魅力は、音楽の経験が全くない人でも楽しめる点にあります。
作曲や楽器演奏といったスキルを持っていなくても、誰でも自分の感性だけで楽曲を作れるという可能性を広げてくれるのです。
たとえば、SNSでオリジナルのBGMを付けたいクリエイターや、YouTube動画のバックミュージックが欲しい人にとって、MusicFXは非常に有用なツールになります。
さらに、楽曲のジャンルや雰囲気も細かく指定できるため、自分好みのスタイルで音楽を楽しむことが可能です。
「音楽って難しそう」
「自分には無理」
と感じていた方にこそ、このツールを試してほしいと思える内容です。
また、現時点では英語ベースの入力が必要ですが、シンプルな英語表現でも十分に反応してくれるため、語学力に自信がなくても安心です。
必要なのは、少しの創造力とワクワクする気持ちだけ。
そう言っても過言ではありません。
音楽理論なしで曲が作れる3つの理由

理由1:テキストベースで音楽を生成できる
MusicFX(旧MusicLM)が提供する最大のメリットは、テキストだけで音楽を作成できるという点です。
通常、作曲には五線譜の知識やコード進行の理解が必要になりますが、MusicFXではそうした専門的な理論は一切不要です。
たとえば
「落ち着いたピアノのインストゥルメンタル」
「疾走感のあるエレクトロニック」
など、自分の感覚に従って言葉を入力するだけで、AIがそれにマッチしたサウンドを自動的に構成してくれます。
入力するのは短い文章やフレーズだけでOK。
その文章がまるで「楽譜の代わり」として機能し、AIがそれを解釈して楽曲を構築するのです。
説明文が「楽譜の代わり」になる仕組み
これは、言語処理AIと音楽生成AIを統合することで実現されています。
MusicFXは、大量の音楽データを学習したうえで
「この言葉はこのような音楽を意味する」
という相関性を把握しています。
つまり、ユーザーの言葉を“音楽的な構造”に変換する翻訳機のような働きをしているのです。
しかも、結果として出力される音源は、単なる効果音ではなく、イントロ、展開、終わりまで含んだ構成された一曲として成り立っています。
「言葉さえあれば曲ができる」という体験は、従来の作曲プロセスとは全く異なる価値を提供しています。
理由2:豊富なジャンルとスタイルに対応
次に挙げられるのが、ジャンルの幅広さとスタイルの多様性です。
MusicFXでは、ポップス、ロック、クラシック、ジャズ、ヒップホップ、アンビエントなど、あらゆるジャンルに対応しています。
しかも、単にジャンルを指定するだけでなく
「80年代風」
「日本的な音階」
「暗めのムード」
といったニュアンスも汲み取ることが可能です。
これにより、自分だけの世界観を音にできるという魅力が生まれます。
ポップスからジャズまで対応する柔軟性
たとえば、YouTubeの動画BGMとしておしゃれなジャズ風の曲を求めるクリエイターや、TikTokに合うテンポの速いEDMを作りたい人にとって、欲しい音を即座に作れる柔軟性は非常に大きな強みになります。
どんな表現でも「伝わる音」に仕上げる力があるため、プロに頼まずとも、自分の手で音楽を「指示する」ことができるのです。
また、ジャンルを掛け合わせた複合スタイルにも対応しており
「ジャズ×エレクトロ」
「和楽器×トラップ」
のようなニッチな構成も生成可能です。
音楽の知識がなくても、多彩なジャンルを操れるという点が、これまでにないユーザー体験につながっています。
理由3:リアルな音質と自然な構成力
最後に、完成された音質と構成力の高さが、MusicFXの優位性を支えています。
「AIの作った音楽」と聞くと、機械的で不自然な印象を抱く人も多いでしょう。
しかし、MusicFXはそうした先入観を裏切る人間らしい抑揚と構成美を持っています。
AIの進化で違和感のない仕上がりに
音質においても、従来のAI音源とは一線を画しており、プロが制作したような自然な音が再現されます。
また、曲の冒頭・盛り上がり・終結といったストーリー性があり、一曲としての完成度が非常に高いのも特筆すべき点です。
これにより、映像制作やSNSでの活用にも即座に対応可能で、「とりあえず流す音楽」としてではなく、演出に深みを持たせることも可能になります。
感情を伝えられる音楽を、自分の言葉から生み出せるという実感は、まさに次世代の創作体験そのものと言えるでしょう。
使い方の基本ステップ

ステップ1:アカウント登録とアクセス方法
MusicFX(旧MusicLM)を使うには、まずGoogleアカウントが必要です。
これはGoogleが提供しているサービスであるため、Gmailアカウントを既に持っていれば、そのままログインするだけでアクセスできます。
公式ページにアクセスし、ログインを求められたらGoogleアカウントで認証するだけなので、登録に時間がかかることはほとんどありません。
ただし、一部の国や地域ではアクセス制限がある可能性があります。
そのため、うまくログインできない場合は、Googleのサポートページを確認することをおすすめします。
現在はまだベータ版の段階で、対象ユーザーが制限されていることもあるようです。
正式公開後にはより多くの人が使えるようになることが期待されます。
ステップ2:音楽生成用のテキスト入力
ログイン後の画面には、テキスト入力欄が表示されます。
ここに、自分がイメージする音楽の特徴や雰囲気を入力します。
例としては、「relaxing piano melody」や「fast tempo electronic beat with synth」などの英語フレーズです。
このテキストが、楽譜の代わりになると考えてください。
英語での入力が基本ですが、難しい文法や表現は必要なく、単語を並べるだけでも十分AIが意図を汲み取ってくれる仕様になっています。
また、ジャンルや感情、使用する楽器などを組み合わせることで、より自分好みの曲が生成されやすくなります。
「japanese traditional flute with ambient background」のように、ニッチな指示も対応可能です。
注意点としては、不適切な表現や過度に抽象的な文は、思った通りの音楽にならないことがあるという点です。
そのため、最初はシンプルで明確な指示から始めるのがコツです。
ステップ3:出力された音源の確認と活用
テキストを入力すると、AIが処理を行い、数十秒から数分で音楽ファイルを生成します。
この段階では、複数のパターンが提示される場合もあります。
いくつか聴き比べて、自分のイメージに最も近い音源を選ぶことができます。
再生ボタンでプレビューしながら微調整もできるため、完成度の高い一曲を仕上げることが可能です。
さらに便利なのが、生成された音源のダウンロードや共有機能です。
一部のバージョンではMP3形式で保存でき、YouTube、Instagram、TikTokなどにそのまま利用できる仕様になっています。
ただし、ここで気をつけたいのが使用許諾の範囲です。
商用利用に対応しているかどうかは、必ず事前に利用規約を確認するようにしてください。
あくまで個人利用やテスト目的での使用であれば問題ないケースが多いですが、プロジェクトや収益化を前提としたコンテンツに使用する際は、Google側のガイドラインを守る必要があります。
必要に応じてクレジット表記なども検討しておくと安心です。
このように、MusicFXの使用はわずか3ステップで完了しますが、その中に創造の可能性がぎゅっと詰まっていると言えるでしょう。
よくある疑問とその回答

無料で使える?商用利用は可能?
MusicFX(旧MusicLM)は、基本的に無料で利用できます。
GoogleのAI実験プラットフォーム「AI Test Kitchen」上で提供されており、登録ユーザーであれば誰でもアクセスが可能です。
ただし、現時点では試験的なサービスのため、一部の機能には制限が設けられていたり、ユーザー登録の審査に時間がかかるケースもあるようです。
商用利用については慎重に確認する必要があります。
生成された楽曲をYouTube動画やSNSに使うこと自体は、個人の範囲であれば問題ないケースが多いですが、収益化を前提としたコンテンツに使用する場合は、Google側の利用規約を事前にチェックすることが不可欠です。
たとえば、MP3としてダウンロードした音源を有料コンテンツに使う場合、ライセンス条項やクレジット表記が必要になる可能性があります。
今後、商用利用向けの有料版やライセンスパッケージが提供される可能性もあるため、最新情報を定期的に確認しておくと安心です。
日本語の説明文にも対応している?
現段階では、MusicFXの入力欄は英語によるテキスト指示を前提としています。
そのため、「やさしいバイオリン曲」や「夏の夕暮れに聴きたいBGM」といった日本語での入力はうまく反応しないケースも報告されています。
しかし、AIの自然言語処理能力は日々進化しており、今後は日本語対応が進む可能性も十分にあります。
一方で
「gentle violin melody」
「nostalgic summer sunset background」
などの簡単な英語であれば、ほとんどの場合で希望に近い音楽が生成されます。
特に音楽ジャンルや楽器、感情表現(happy, sad, calm, energeticなど)は、シンプルな単語だけでAIが意図を汲み取ってくれるため、英語に自信がなくても安心です。
また、オンライン翻訳ツールを活用すれば、日本語で思いついたフレーズを簡単に英語に変換できます。
言葉の壁を感じる必要はなく、むしろ創造力をそのまま形にできる自由さが魅力です。
他のAI音楽ツールとの違いは?
AIを活用した音楽生成ツールは年々増えており、SoundrawやAIVA、Amper Musicなどが有名です。
それらのツールと比較したとき、MusicFX(旧MusicLM)の最大の特徴は「テキストだけで生成できる手軽さ」にあります。
多くの他社ツールは、音楽理論に基づいた構成ブロックの選択や、楽器ごとの細かなパラメータ設定を求められるため、どうしても制作工程に時間がかかってしまいます。
一方、MusicFXは「説明文」さえあれば、AIがすべてを自動で構成してくれるため、音楽経験がまったくない人でも直感的に操作できます。
また、Googleが開発しているという安心感や、圧倒的な研究開発力に支えられたクオリティも大きな魅力です。
さらに、日々アップデートが加えられているため、ユーザーのフィードバックが今後の改善に直結しやすい点もメリットといえるでしょう。
ただし、他のツールと比べて「カスタマイズ性」や「楽曲構成の自由度」が限られる面もあり、本格的な作曲を求めるユーザーには物足りなさを感じる可能性もあります。
そのため、MusicFXは“アイデア出し”や“短時間でのBGM生成”といった用途に特化したツールとして活用すると、効果的です。
注意点とトラブル回避のポイント
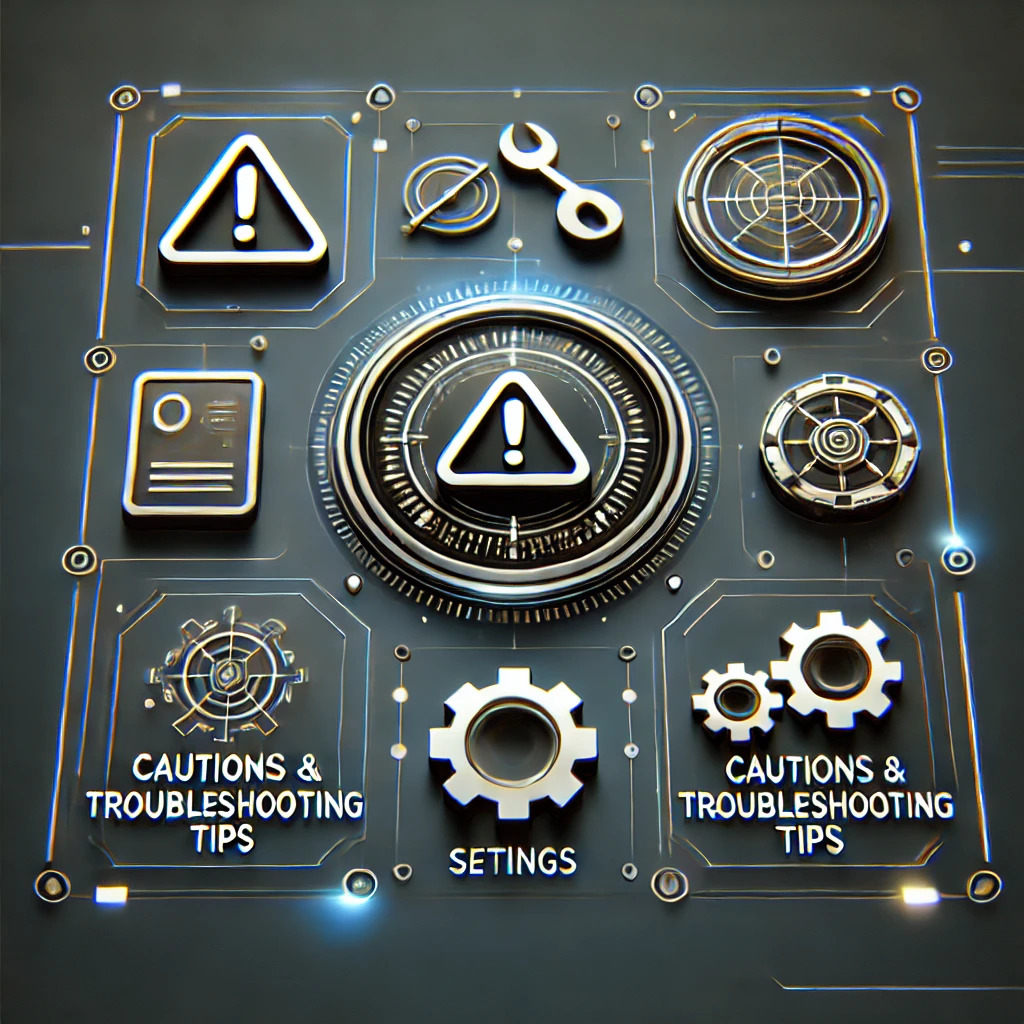
生成結果に不満があるときの対処法
MusicFX(旧MusicLM)を使っていて
「イメージと違う曲が出力された」
と感じる場面は少なくありません。
これは、AIがテキストから音楽を生成する仕組みである以上、指示した言葉のニュアンスや構成が抽象的すぎると、狙った通りの結果にならないことが理由です。
たとえば「美しい旋律」や「心が落ち着く曲」といった漠然とした表現では、AIはどういう構成で、どんな楽器を使い、どのテンポで進行させればよいのか判断がつきにくくなります。
そのため、望んだ曲にならなかった場合は、指示文をより具体的にしてみるのがポイントです。
「slow tempo」
「soft piano」
「ambient background」
など、テンポ、楽器、雰囲気を要素ごとに記述することで、AIは的確に構成を組み立てやすくなります。
また、一度で理想の楽曲が出てこないのは珍しいことではなく、複数回の試行を前提に活用するのがコツです。
もし、全く違うジャンルの音楽が出てくるようであれば、使用している英単語が別のジャンルに強く紐づいている可能性があります。
そういった場合は、AIが連想しやすい単語を避ける、または別の言い回しを試してみると、精度の高い結果に近づけます。
AIと対話しながらチューニングするような感覚で、少しずつ理想の音に近づける工程を楽しむことが大切です。
著作権や使用範囲で気をつけたいこと
AIが生成した音楽は誰のものか?
というのは、現在多くの分野で議論されているトピックのひとつです。
MusicFXでは、出力された音源が利用規約においてどのような扱いになっているかを、必ず確認する必要があります。
基本的には、個人の範囲での使用や非商用利用は許可されているケースが多いですが、それが商業活動に発展した瞬間に制限がかかる場合も少なくありません。
たとえば、生成された楽曲をそのまま商用アニメやゲームに使用したり、有料のサウンドパックとして販売するような行為は、Googleの規約違反に該当する可能性があります。
また、AIが過去の膨大な音楽データを学習している以上、偶然、既存の楽曲と酷似したメロディや構成が生成されるリスクもあります。
このようなケースでは、ユーザーが責任を問われる可能性があるため、生成された音楽を公開・販売する場合は慎重な判断が必要です。
特にYouTubeなど収益化メディアでの利用を考えている場合は、動画内に「AIによって生成された楽曲を使用」といった表記を加えることや、権利的にグレーゾーンとなり得る箇所を避けるといった配慮が求められます。
トラブルを未然に防ぐためにも、常に公式の利用ガイドラインを最新の状態で把握しておくことが大前提です。
また、将来的には著作権付きの商用ライセンス付きプランが登場する可能性もあるため、今のうちから動向を注視しておくと安心です。
まとめ~MusicFX(旧MusicLM)は誰でも始められる音楽革命~

自分の言葉で音楽が作れる時代へ
かつて音楽制作といえば、限られた一部の人だけができる高度なスキルとされていました。
作曲ソフト、音楽理論、機材知識……そのすべてを揃えなければ「1曲を生み出す」ことすら叶わなかった時代。
しかし今、その常識が静かに崩れつつあります。
GoogleのAIツール「MusicFX(旧MusicLM)」は、ただ“思い浮かべた音楽”を、言葉にして伝えるだけで、その場で再現してくれるという革新をもたらしました。
もう、スケールやコード進行を覚える必要はありません。
感じたイメージをそのまま言葉に変えて、音楽にする。
そんな創作が、これからの標準になっていくのかもしれません。
自分の内にある感性をもっと気軽にアウトプットしたい——
そんな願いに、これ以上ない形で応えてくれるツールが、MusicFXです。
まずは試して、新しい創作の楽しさを体験しよう
実際に使ってみなければ、その魅力は語り尽くせません。
登録は無料。
難しい操作は一切なく、英語が苦手でもシンプルな単語の組み合わせで十分伝わります。
たとえば
「calm piano」
「dreamy synth」
「japanese vibe」
──ほんの数ワードが、あなたの創造の扉を開いてくれるのです。
生成された音楽は、SNSのBGMやYouTubeの挿入音源として使ったり、自分だけのリスニング素材として保存したりと活用方法も豊富です。
もちろん、著作権や商用利用についての注意点はしっかり確認しておく必要がありますが、それを踏まえたうえでの自由な創作は、まさに新時代の楽しみ方。
「音楽を作るなんて自分には無理」と思っていた方にこそ、一度体験していただきたい、それがMusicFXというツールです。
音楽に触れる手段が“演奏”や“打ち込み”ではなく、“言葉”になった今、表現のハードルは限りなくゼロに近づいています。
まだ試していないなら、今この瞬間がチャンスかもしれません。
まずはアクセスして、気軽に一曲生み出してみてください。
その一曲が、あなたにとって“音楽って、意外とできるんだ”という気づきになるはずです。
そして、その気づきが、未来の創作につながる第一歩となることでしょう。
最新情報はXで発信中!
リアルな声や速報は @ZeroAiFrontier でも毎日つぶやいています!




コメント