ごきげんよう。
「ゼロからのAIフロンティア」へようこそ。
当ブログを運営しているケンタロウです。
今回は『音楽生成AI』と云う事で紹介いたします。
筆者は作曲家として、バンド活動をしております。(プロフィール参照)
作曲をする上で、1曲丸々AIに頼った事はありませんが、バンドメンバーにデモ曲(発表前のメンバー間だけでやり取りする音源)で、簡易演奏やアイデア出しに使ったりする事はあります。
さて、「音楽生成タイプAIって本当に使えるの?」
そんな疑問を抱いたことはありませんか?
実際、プロの現場でもAIを取り入れる動きが広がっており、独自の楽曲を自動で作曲する時代がすでに始まっています。
この記事では、音楽生成タイプAIの基本的な仕組みから、実際の活用シーン、どんな人におすすめかまでをわかりやすく解説していきます。
AI初心者でも安心して読める内容になっていますので、「AIで音楽制作をもっと自由にしたい!」という方は、ぜひ最後までご覧ください。
音楽生成タイプAIとは?基本概念と注目の理由

音楽生成タイプAIとは何か?
音楽生成タイプAIとは、人工知能が人間の代わりにメロディ、コード進行、リズムパターンなどを自動で作曲してくれる技術のことです。
その技術の中核には、ディープラーニングやニューラルネットワークといったAIの学習アルゴリズムがあり、過去の膨大な音楽データをもとに「曲の構造」や「ジャンルの特徴」「ヒットしやすいパターン」を学習しています。
近年では、ユーザーが数クリックで作曲できるようなインターフェースが登場し、専門的な知識がなくても楽曲制作が可能に。
まるで料理のレシピを選ぶように、ジャンルやテンポ、雰囲気を設定するだけで、AIが自動で曲を作ってくれる時代になりました。
しかも、その出来栄えは一昔前の「機械的な音」ではありません。
人間が作ったような“感情”のあるメロディや展開すら生成できるようになっているのです。
つまり、音楽生成タイプAIは「ゼロから曲を生み出す力」を持った、次世代の音楽ツールだと言えます。
なぜ今、音楽生成AIが注目されているのか
理由はシンプル。
音楽制作にかかる「時間・コスト・スキル」の壁をAIが取り払ってくれるからです。
これまでは、1曲を完成させるまでに膨大な時間と試行錯誤が必要でした。
作曲ソフトの操作を覚え、楽器演奏や理論の勉強を重ねる必要がありましたが、それがAIによって劇的に変わりました。
例えば、YouTubeクリエイターが動画用のBGMを数分で用意したい時、AIを使えば簡単にニーズに合った音源が手に入ります。
ゲーム開発者、広告制作者、ポッドキャスター…あらゆる分野の“非作曲家”たちが、音楽の可能性を広げられるようになったのです。
さらに、AIは24時間365日、疲れ知らずで作曲し続ける存在。
人間の感情やインスピレーションに左右されないため、複数のパターンを同時に生成することも容易です。
また、AI生成楽曲は「著作権の取り扱いが明確」なケースが多く、商用利用しやすいというメリットも。
音楽の民主化を後押しする革新技術として、多くの業界から注目を集めているのです。
従来の作曲とAI作曲の違いとは
音楽生成タイプAIの最大の違いは、「感覚や経験に頼らず、ロジックと統計に基づいて作曲する」という点です。
人間による作曲は、インスピレーションや感性、時には偶然から生まれるアート的な側面が強い一方、AIは過去のデータから「最も心地よく聴こえる構成」や「ヒットしやすいメロディパターン」を数学的に導き出します。
AIはパターン認識が得意で、人間が気づかない音の流れや展開を提案してくれることがあります。
これは、作曲初心者だけでなく、プロの作曲家にとっても「新しい刺激」となり得るのです。
ただし、現時点でAIは“完全に人間の代替”とは言えません。
音楽に必要な「感情の揺れ」や「意図的な不協和音」、「表現の間」など、あえてルールを崩すような創造性は、人間の手による後加工や監修が求められる場面も多いのが現状です。
しかし、その一方で、AI作曲を「土台」として活用することで、創作の幅を格段に広げられるという事実は見逃せません。
まさに、AIは「作曲の相棒」としての立場を確立しつつあるのです。
このように、音楽生成タイプAIは、音楽をもっと身近で自由にする可能性を秘めたツールです。
では。実際にどんな場面で、どんな風に活用されているのか?
次章では3つの具体的な活用術を詳しくご紹介していきます。
音楽生成タイプAIの3つの活用術
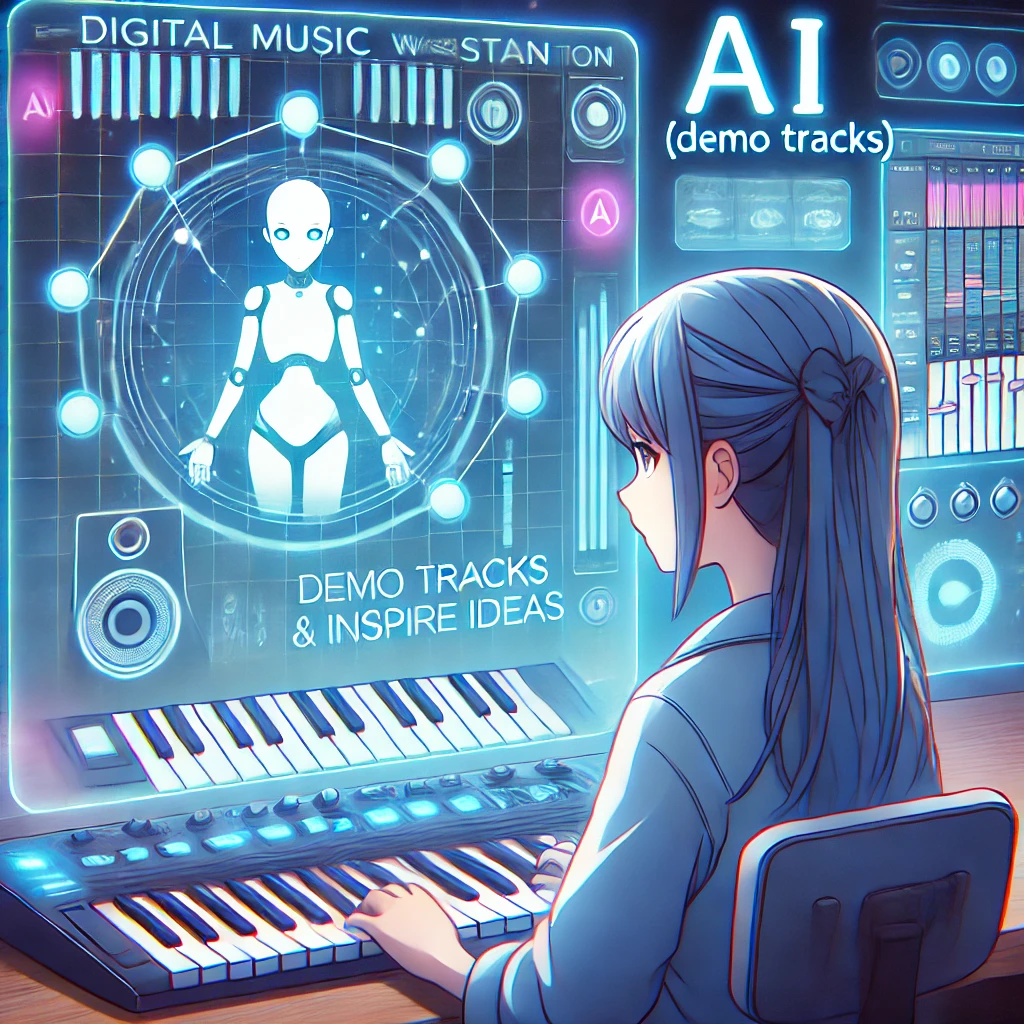
デモ制作やアイデア出しに活用する
音楽生成タイプAIは、作曲の初期段階における「アイデアの種」として圧倒的な力を発揮します。
筆者自身も、バンドでの新曲制作に入る前に、簡易的なフレーズをAIで作成し、メンバーに共有することがあります。
全体の構成を決める前の段階で、リズムやコード進行の可能性をスピーディに探れる点がとても魅力です。
音楽の制作において、「何から手をつけて良いかわからない」と感じた瞬間に、AIが提示してくれる断片的なメロディが大きな創作のヒントになることがあります。
人間の感性と異なる発想が浮かぶため、固定観念を壊してくれる存在とも言えるでしょう。
特にポップスやロックのように、コードの進行や構造がある程度パターン化されているジャンルでは、AIによるデモ制作は“スピードと効率”の両立を叶えてくれる、現代作曲家の強力な相棒です。
即興メロディやリズムの生成が可能
生成AIの進化により、単なるコード進行の提案にとどまらず、ビートやドラムパターン、ベースラインまでもリアルタイムで生成できるようになりました。
この技術を活かすことで、DTMや打ち込みに不慣れなユーザーでも、ある程度完成度の高い音源を短時間で作ることが可能です。
「何となく頭に浮かんだメロディを形にする」そんな場面でも、AIは即時に形にしてくれる“音のスケッチブック”となります。
BGM制作やコンテンツ制作に活用する
音楽生成タイプAIは、商用・コンテンツ制作の現場でも重宝されています。
たとえばYouTuberや動画編集者が、毎週更新される動画に合うBGMを毎回探すのは、手間もコストもかかる作業です。
しかし、AI作曲ツールを活用すれば、「元気系」「癒し系」「シネマティック」など、動画の雰囲気に合わせたBGMを瞬時に生成可能。
著作権フリーの音源が多く、収益化済みのチャンネルでも安心して使用できるのは大きな利点です。
YouTube動画やゲーム、広告音楽にも最適
動画以外にも、AI作曲はゲーム開発やアプリ内BGM、ウェブCMなどにも応用が効きます。
従来なら外部の作曲家に発注し、数週間の納期と高額なコストが必要だった場面も、AIを使えばその日のうちに音源を用意できます。
たとえば、ノベルゲームのシーンに合わせて、緊張感あるBGMや感動的な旋律を即時生成することも可能です。
さらに近年では、広告制作会社でも、映像にマッチする「尺合わせ済み」の楽曲生成が求められており、AIの活用は年々増えています。
音楽の“発注→修正→納品”という煩雑なプロセスが短縮されるため、コストパフォーマンスの観点でも非常に優秀です。
作曲初心者の学習ツールとして使う
これから作曲を始めたい初心者にとっても、音楽生成タイプAIは最良の先生になり得ます。
音楽理論やコード進行を一から学ぶのは、正直なところハードルが高いもの。
ですが、AIで作成された曲を分析することで、「このジャンルでは、こういう進行が多いんだ」といった傾向を、体感的に学ぶことができます。
AIが提示する楽曲構造には、黄金比やポピュラー音楽の王道進行が多く含まれており、自然に理論を吸収できる点が初心者にとっての強みです。
楽曲構成や和音の理解を深められる
たとえば、コード進行が変化する場面や、サビ前での転調のテクニックなどは、AI楽曲を再生しながら耳で感じることができます。
音楽学校で教わるような内容を、“聴いて・触って・真似て”学べるのがAIの強みです。
理屈だけでなく実践を通して吸収できるので、「理論でつまずいた人」にとって救いとなる存在になるはずです。
加えて、DAW(音楽制作ソフト)との連携ができるツールも多く、AIで作ったベースに自分のフレーズを加えることで、唯一無二の曲に仕上げることも可能です。
このように、音楽生成タイプAIは、初心者からプロ、動画編集者や広告制作者まで幅広く活用できる汎用性の高いツールです。
次は、どのツールが実際におすすめなのか?
注目のAIツールを比較しながら解説していきます。
実際に使える音楽生成AIツールの比較
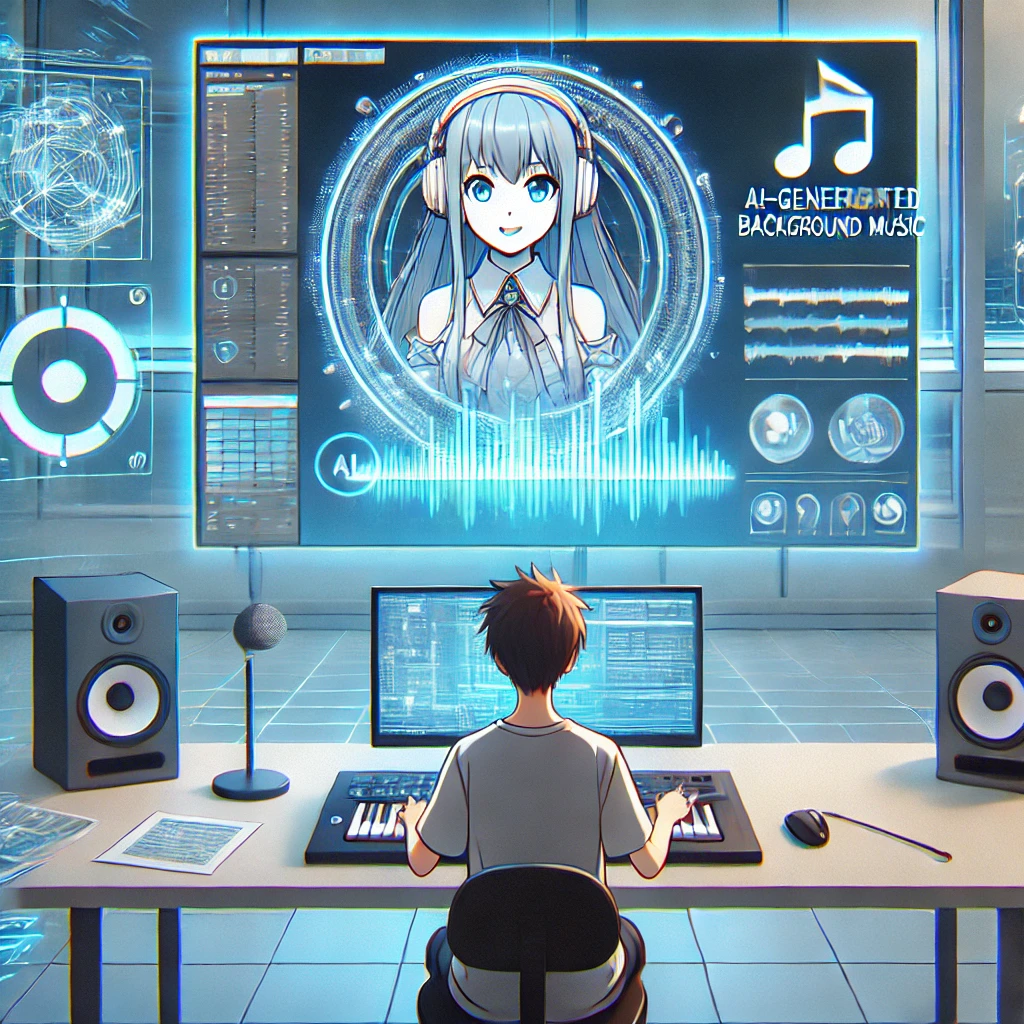
人気ツール3選(特徴・料金・使い勝手)
音楽生成タイプAIが注目される中、実際にどのツールを選べば良いのか迷ってしまう方も多いはずです。
ここでは、筆者が実際に使用した中で、特に満足度が高かった3つのツールを紹介します。
まず注目すべきは、使いやすさと完成度の高さで評価されている「Soundraw(サウンドロー)」です。
直感的な操作で「シーン」「ジャンル」「テンポ」などを選ぶだけで、数クリックでクオリティの高いBGMが生成されます。
商用利用も可能で、著作権の問題がクリアになっているのも嬉しいポイント。
YouTubeや企業CM向けにBGMを探している方にはぴったりのサービスです。
月額は約1,650円(税込)と有料ですが、成果に対するコストパフォーマンスは非常に高いと感じました。
次に紹介したいのが、初心者でも扱いやすいインターフェースを誇る「Amper Music」です。
こちらはAIが生成する楽曲をパーツごとに調整できる柔軟性があり、個人制作からプロの現場まで幅広く対応できます。
無料で試せる範囲が広く、英語圏ツールながら感覚的に操作できる設計になっています。
海外のゲーム開発者や独立系映像クリエイターにも利用されており、BGMの「細かな調整」にこだわりたい人には非常に向いています。
最後に紹介するのが「AIVA(アイヴァ)」。
クラシックや映画音楽のような構築的な音楽を得意とし、AIとは思えないほど緻密な構成で楽曲を生成してくれる点が魅力です。
特に編曲やオーケストラに近い雰囲気を出したい方におすすめ。
こちらも商用ライセンスが明確で、プロジェクト単位で購入できるプランもあり、用途に応じた柔軟な選択が可能です。
このように、音楽生成タイプAIツールはそれぞれ得意ジャンルや使用感が異なるため、目的に合わせた選定が重要です。
ツール選びのポイントとは?
では、数ある音楽生成タイプAIの中から、どのように自分に最適なツールを選べば良いのでしょうか。
筆者が実際に複数のサービスを使って感じた、選び方の“本質”をお伝えします。
まず大切なのは、「その音楽がどんな場面で使われるか?」を明確にすることです。
たとえば、YouTube動画のBGMとして使いたいのか、自作の楽曲にメロディだけを補強したいのか、それとも学習目的なのかで選ぶべきツールは変わります。
一見どれも似たようなAI作曲ツールに見えても、出力される曲のテイストやライセンス、編集の柔軟性などに大きな差があるため、目的に合った軸を持つことがとても重要なのです。
さらに、DAW(音楽制作ソフト)との連携が可能かどうか、MIDIファイルでの出力に対応しているか、といった「拡張性」も見逃せません。
将来的に本格的な音楽制作に挑戦する予定があるなら、カスタマイズ性の高いツールを選ぶべきです。
自分の目的に合った機能を見極める
具体的には、作業時間を短縮したい動画編集者には、ワンクリックでBGM生成が可能な「Soundraw」が最適です。
一方で、楽曲構造を細かく設計したい作曲志向の方には、「AIVA」や「Amper Music」の方が合っています。
ツールの「自由度」と「自動化のバランス」は、制作目的によって最適解が変わるもの。
特に副業や趣味で音楽を始める人は、まずは「無料で試せる範囲が広いツール」からスタートするのがおすすめです。
また、多くのツールには商用利用の制限があるため、ライセンス情報の確認も忘れずに。
AIが作ったからといって、すべて自由に使えるわけではありません。
筆者も過去に、商用不可のデモ音源をYouTubeで使用してしまい、収益化が一時的に停止された経験があります。
このような失敗を避けるためにも、ライセンス表記や利用条件の読み込みは絶対に怠らないようにしましょう。
ここまで、実際に使える音楽生成タイプAIツールの違いや選び方のポイントを紹介してきました。
ただ、どんなに便利なツールでも“万能”ではありません。
次の章では、音楽生成AIの限界と注意点について、具体例を交えて解説していきます。
音楽生成AIを使う際の注意点と限界

著作権と商用利用の問題
音楽生成タイプAIを使う際に、まず気をつけるべきなのが「著作権と商用利用」に関するルールです。
「AIで自動生成された曲だから、自由に使っていい」と考えるのは、実は非常に危険な誤解です。
多くのAI作曲ツールでは、生成された楽曲に対する権利の所在があらかじめ明記されています。
たとえば、無料プランでは商用利用不可、有料プランでは利用可能といったケースもあり、使用条件を確認せずに動画や広告に使ってしまうと、トラブルのもとになります。
筆者も以前、Soundrawで生成した楽曲をYouTube動画に使用した際、プランの条件を読み違え、一時的に収益化が停止されるという失敗を経験しました。
こうしたリスクを避けるためにも、各サービスの「利用規約」「著作権に関するポリシー」を必ず確認し、自分の使い方に合ったプランを選ぶことが重要です。
完全依存はNG?人間の感性とのバランス
どれだけ高機能でも、音楽生成タイプAIに“完全に頼る”のはおすすめできません。
理由はシンプルで、AIはあくまで“データの集合体”であり、「今この瞬間の空気感」や「感情の揺れ」を自発的に捉えることはできないからです。
AIは過去の音楽からパターンを学び、その傾向に従って曲を構築します。
しかし、そこに「個性」や「人間らしいムラ」がない場合、どこか無機質で似通った作品に仕上がってしまうことがあります。
「なんとなく綺麗だけど、心に残らない」──そんな印象を持つAI楽曲が多いのも事実です。
ですから、AIは“補助ツール”として活用し、人間の感性や意図を加えて初めて「生きた音楽」になります。
ゼロからのAIフロンティアでも、筆者はAIをベースにしつつ、後から自分のコードやアレンジを加えるというスタイルを推奨しています。
AIが得意なのは“効率と再現性”、人間が得意なのは“偶然性と情緒”。
両者をどう融合させるかが、今後の音楽制作の鍵になるでしょう。
精度やクオリティには差がある
すべての音楽生成タイプAIが、同じレベルで曲を生み出せるわけではありません。
たとえば、メロディの構成力に優れたツールもあれば、コード進行が不自然だったり、リズムが単調だったりするものも存在します。
これは、ツールによって「学習しているデータの質」や「AIモデルの種類」が異なるためで、ユーザーのニーズに合わない場合、むしろ手直しの手間が増えることもあるのです。
筆者も、某AI作曲サービスを試してみた際、出力された楽曲のテンポ感が全体的にズレており、DAWで調整する手間がかえって増えてしまったことがあります。
そのため、最初から「完璧なものを期待しすぎない」という意識が重要です。
AIの出力をそのまま使うより、土台として使い、自分なりの調整を加えるというスタンスが最も成果に繋がりやすいと感じています。
特に商用制作や長尺の作品では、「細部のクオリティ」が作品全体の印象を左右します。
そうしたときにこそ、AIの“限界”を知っておくことが、クリエイターとしての信頼感にも繋がるのではないでしょうか。
ここまで、音楽生成タイプAIを使う際に注意すべきポイントと、見落とされがちな限界について解説してきました。
次は、読者からよく寄せられる質問に答えるQ&Aコーナーに進みましょう。
よくある質問(FAQ)

音楽生成AIだけでプロ並みの曲は作れる?
答えは「半分YES、半分NO」です。
音楽生成タイプAIは、一定レベルの楽曲を自動で作り出す力を持っていますが、すべてを任せてプロ品質に仕上げるのは難しい場面も多いです。
たとえば、YouTubeのBGMや広告用の短尺音楽であれば、AIが作っただけの楽曲でも十分に通用するシーンがあります。
実際、筆者の知人でも「Amper Music」だけで収益化動画を制作している方もいます。
ただし、3分以上の構成がしっかりした楽曲や、感情の抑揚が求められる歌モノになると、どうしても“人間の手”が必要になることが多いです。
AIはあくまで“たたき台”であり、そこに作家の視点や演奏技術が加わって初めて「プロの作品」に昇華されるというのが現場の実感です。
つまり、AIを導入すれば誰でも一瞬でプロになれるというわけではありませんが、「プロのクオリティに近づくための時間と労力を大幅に短縮できる」ことは間違いありません。
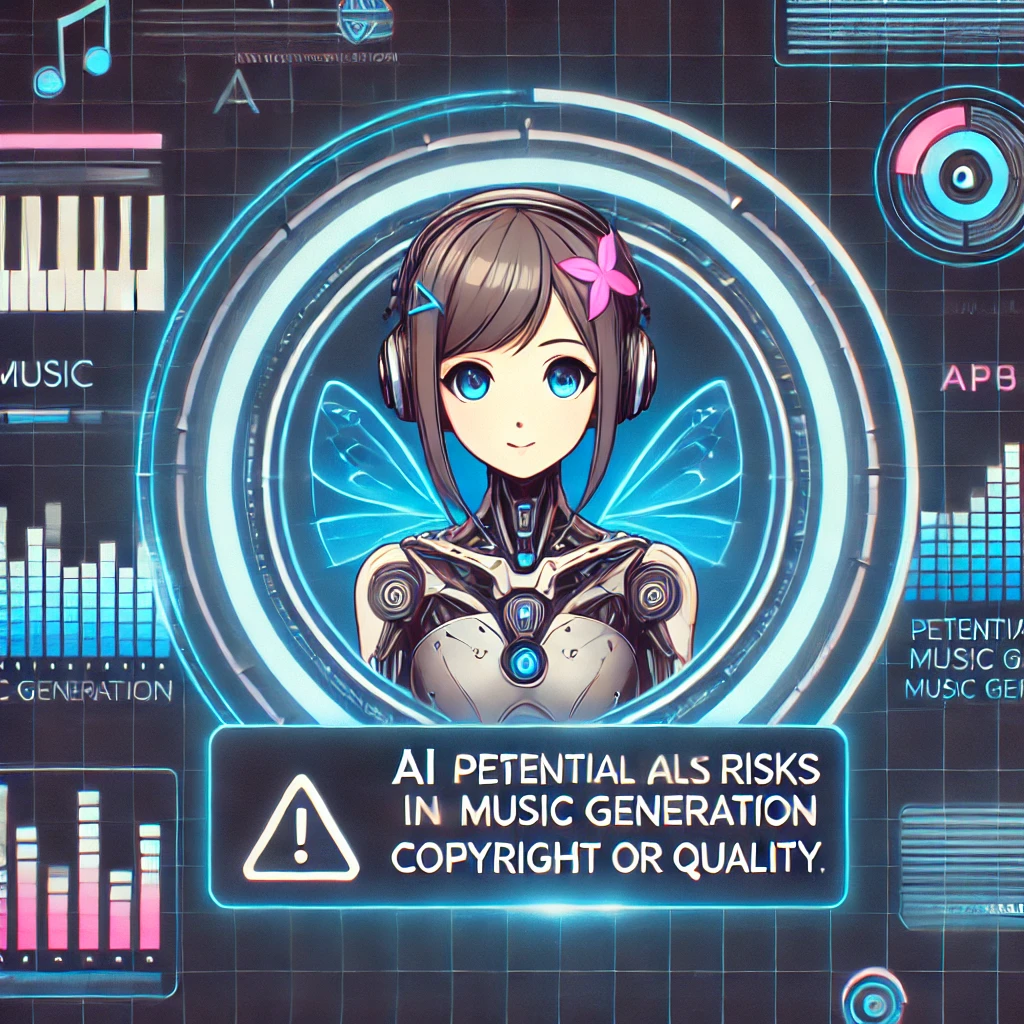
英語圏のツールでも日本語楽曲に対応できる?
基本的には対応可能ですが、いくつか注意が必要です。
多くの音楽生成タイプAIは英語圏で開発されているため、UIが英語で提供されていたり、音楽データが欧米ポップス基準で学習されているという点があります。
そのため、日本語のメロディや詞を前提に作る場合
「コード進行やメロディラインがやや英語っぽい」
仕上がりになることがあります。
この“違和感”を補正するには、自分で旋律を編集したり、リズムやアクセントを調整する作業が欠かせません。
たとえば、筆者が「AIVA」で日本語歌詞をもとに作曲した際、AIが生成したメロディに日本語の“語感”が乗りにくく、サビの歌詞が不自然に聞こえてしまった経験があります。
とはいえ、コード進行や伴奏の構築には非常に役立つため
「日本語ボーカル曲のベース作り」
にAIを使い、細かいニュアンスは自分で仕上げるという使い方が効果的です。
無料で使えるおすすめツールはある?
はい、無料でも使える音楽生成タイプAIは複数あります。
ただし、機能や商用利用の範囲には制限があります。
筆者が実際に使用してみて、無料で特に優れていると感じたのが「Soundraw(無料トライアル)」と「Amper Music(登録不要で試用可能)」です。
Soundrawは、登録後すぐに楽曲の生成と試聴ができるのが特徴で、クオリティも商業レベルに近いものが揃っています。
ただし、楽曲のダウンロードや商用利用には有料プランへの切り替えが必要です。
一方で、Amper Musicはブラウザベースで動作が軽く、音楽制作初心者でも迷わず操作できる設計になっており、英語ながらも感覚的に操作できます。
「まずはAIでどんな曲が作れるのか試してみたい」という方には、最適な選択肢です。
また、海外では「Boomy」や「Ecrett Music」なども人気で、いずれも基本機能は無料で利用可能です。
ただし、無料版ではMP3の出力不可や透かし音源の挿入など、制約があるケースも多いため、用途に応じた見極めが大切になります。
ブログや副業で収益化を目指すなら、有料プランを前提に使ったほうがトラブルも少なく安心です。
以上、読者の皆さんからよく寄せられる質問をまとめてお答えしました。
音楽生成タイプAIの理解がより深まったかと思います。
最後に、この記事の総まとめと次のアクションをお届けします。
まとめ~音楽生成タイプAIで、もっと自由な音楽制作を~

AIを味方につけて、自分だけの音楽を楽しもう
音楽生成タイプAIは、誰もが“自分らしい音楽”を自由に表現できる時代をつくる革新的な存在です。
これまで音楽制作といえば、一部の専門家や限られた人材のための領域でした。
高価な機材、理論の習得、演奏スキル…。そうしたハードルの数々が、創作の自由を狭めていたのも事実です。
しかし、今ではAIの力を借りれば、コード進行の知識がなくても、ピアノが弾けなくても、自分だけのオリジナル曲を生み出せる。
まるで筆一本でキャンバスに絵を描くように、音の世界と対話できるようになったのです。
AIはあなたの代わりではなく、あなたの“音の相棒”として、創作の世界を支えてくれます。
技術はあくまで手段。
目的は「自分の音楽で誰かの心を動かすこと」ではないでしょうか。
AI音楽ツール徹底比較
これまで紹介してきたように、音楽生成タイプAIには多くのツールがあります。
それぞれに得意分野や個性があり、ユーザーの目的に応じた使い分けが重要です。
Soundrawは映像向けBGM生成に特化し、操作性も抜群。Amper Musicは楽曲構造の編集自由度が高く、初心者からプロまで対応。
そして、AIVAは、まるで映画音楽のような壮大な世界観を描ける本格派です。
それぞれのツールには、無料で試せる範囲も設けられているため、「気軽に試して、比べてみる」ことが成功への第一歩になります。
大切なのは、どのツールが流行っているか、ではなく「自分の創作スタイルにフィットするか」という視点です。
これからAIを取り入れる方は、ぜひ以下の記事も参考にしてみてください。
比較を通して、自分にぴったりの“音のパートナー”が見つかるはずです。
筆者より、作曲者としての意見
冒頭でも伝えた通り、筆者は作曲家としてバンド活動をしています。
ドラム、ギター、ベースといった楽器はすべて演奏可能ですので、AIによる作曲は、あくまで「簡易的サポート」として活用しています。
筆者が思うに──音楽生成タイプAIは確かに便利です。
…ですが!
あまりに依存しすぎると「想像力の欠如」を招いてしまうのではないか、という懸念も抱いています。
話は少し逸れますが、現代ではスマートフォンの普及によって、辞書を引く機会が減り、漢字が書けない人が増えていると耳にしたことはありませんか?
つまり、便利だからといって、すべてを任せきってしまうと「本来持っていた力」を失ってしまう──そんな危うさが、音楽の現場でも起きる可能性があると思うのです。
もちろん、楽器が弾けなくても、AIを使って作曲すること自体は素晴らしいことだと思います。
表現したい想いや世界観があるなら、その手段としてAIを使うのは正しい選択だと心から感じています。
だからこそ、AIを「自分の個性を引き出すツール」として、時間を効率よく使いながら、自分だけの音楽を形にしていってほしい。
このブログを読んでくれたあなたにとって、音楽生成タイプAIが“良き相棒”になることを願って──ほんの少しでも、何かのヒントになれば幸いです。
もっと筆者の音楽に触れてみたい方は、YouTubeチャンネルもぜひチェックしてみてください。
AIを使った曲も公開中です!
最新情報はXで発信中!
リアルな声や速報は @ZeroAiFrontier でも毎日つぶやいています!




コメント